群青の石とロマン(PART 1)
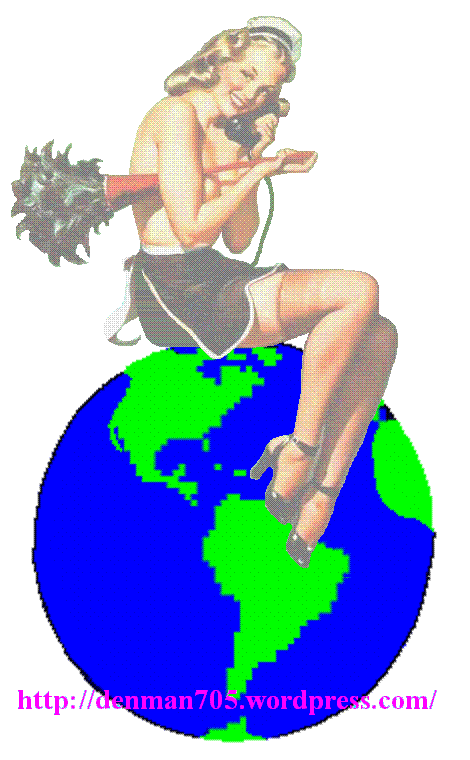
(maid12.gif)
ラピスラズリ

ラピスラズリ (lapis lazuli) を僕がいつも使っている三省堂の国語辞典で引いても出てないんですね。
英辞郎 on the Webで引くと次のように出ています。
《鉱物》 ラピスラズリ 12月の誕生石
三省堂のコンサイス英和辞典には次のように出ています。
《鉱》 瑠璃; 青色顔料; 瑠璃色。
僕は瑠璃と言うのは聞いたことがありますが、ラピスラズリという言葉は知りませんでした。
この石が12月の誕生石だということも知りませんでした。
僕が初めてこのラピスラズリに出くわしたのはクレタ文明を調べていたときです。
参考書の中に出てきたlapis lazuliという単語が分からず、これを辞書で引いたら「瑠璃」と出ていたわけです。
「石」と言ってしまっては身も蓋もないんですよね。
実は、この石は宝石として最も古くから装飾に使われている石のひとつです。
ラピスはラテン語で石を意味します。
ラズリは青という意味です。
ですから「青い石」となりますね。
ラズリは、アラビア語の、天・空・青を意味する“allazward”から派生しました。
このアラビア語はペルシャ語の紺碧色に由来する“lazward”が語源です。
フランス語の“azur”は、“l” が冠詞であるかのように扱われ、ラテン語から脱落して生まれたものです。
スペイン語やポルトガル語で青を意味する“azul”もここから来ており、イベリア半島が8〜13世紀半ばまでイスラム世界であった名残りです。
このラピスラズリの鉱物名はラズライト(lazurite)と呼ばれます。
産地が数カ所しかない貴重な鉱物で、変成作用を受けた石灰岩の中に見つけることが出来ます。

青色の原因はイオウです。
ラズライト中にイオウが過剰に存在すると、イオウは鉄と結びついて金色の黄鉄鉱を形成します。
右側の標本の金色部分が黄鉄鉱です。
白色の部分は方解石です。
黄鉄鉱のみ含んでいるものが重宝されています。
いわゆる“金色の斑点が輝く群青の石”です。
このラズライトが取れる有名な鉱山がアフガニスタンのバダフシャン(Badakhshan)です。
この産地のバダフシャンは有史以前から知られており、現在も最良の原石が採れる最大の鉱山です。
長いあいだ唯一の鉱山でしたが、最近ではロシアのバイカル湖畔やチリの鉱山でも採取されています。
ラピスラズリは日本名を青金石といい、古くは瑠璃(るり)と呼ばれていました。
この瑠璃は星の瞬く夜空を連想させる美しい宝石であったようで、5000年以上も前から珍重されていたんですね。

エジプトでは、紀元前3000年頃の墳墓から、エジプトでは産出されないラピスラズリの装飾品や工芸品が数多く発見されています。
ナイル河畔の町ルクソールの対岸にある王家の谷で発見されたツタンカーメン王(紀元前1350年頃)の黄金マスクにもラピスラズリが使われ、当時のままの美しい金と青のコントラストを見ることができます。
また、太陽と再生のシンボルである虫スカラベやオシリス神の鷹の頭を持つ息子ホルスの目にラピスラズリが使われています。
古代エジプト人はラピスラズリの持つ超自然的な力が病気にも効くと考えたようです。
眼病や鬱病、頭痛などの際に粉末にして塗布したり服用したりしたということがパピルスに書かれています。
この薬としての効用が後に伝えられたようで古代ギリシャ人やローマ人は強壮剤として、または下剤として使用していました。

メソポタミアでは、紀元前2500年頃、チグリス・ユーフラテス河のデルタ地帯に存在したシュメール人の古代都市国家ウル(現在はイラク)の遺跡のプアビ女王墓からラピスラズリのネックレスが出土しました。
淳子さんにその模造品を身に着けてもらいました。
なかなか見ごたえがありますね。
でも、なんだか重そうですよね。(笑)
ラピスラズリとカーネリアン(紅玉髄)のビーズが付いた黄金の頭飾りなども同じ墓から多数発見されました。
聖書の中にもラピスラズリのことが書かれています。
旧約聖書の出エジプト記には、祭司の装飾品のひとつである胸当てにはめ込む石として青い石(Sappir)ラピスラズリの記述を見ることができます。
また新約聖書のヨハネ黙示録には、世界が終末を迎えた後現れるとされる新エルサレムの都の神殿、東西南北12の礎にはそれぞれ12種類の石で飾られ、そのうちの2番目がラピスラズリであると書かれています。
この12種の石が現在の誕生石の元となったそうですよ。
ラピスラズリは12月の誕生石なんですね。
どうして12月なのか?そこまでは調べていません。
もし、分かったら教えてください。
古代ギリシャおよびローマ時代からルネッサンスにかけて、ラピスラズリは、永続性のある群青色の顔料を作るために、細かく砕かれ有名な油絵に使われました。
ただ残念な事に時とともに色が濃くなってしまいます。
古い油絵の多くが黒ずんで見えるのは、このためです。
ルネサンス期、ヨーロッパではラピスラズリは「ウルトラマリン(海の向こうから来た青)」と呼ばれたんですね。
群青色の顔料として珍重されました。
ラピラズリから抽出したこの顔料は他のものでは同じ色を出すことができず、金と等価で取引されるほど高価なものだったそうです。
画家たちはこの鮮やかな青を聖処女マリアと子イエス・キリストのローブのみに使っていた時代もあったほどです。
1828年にフランス人のJ.B.ギメ(西暦1795-1871)が人工的にウルトラマリンを合成することに成功してから、顔料としての需要は急速に衰退します。

日本では、ラピスラズリは瑠璃と呼ばれ、仏教の七宝(金・銀・瑠璃・玻璃・しゃこ・珊瑚・瑪瑙)のひとつとされました。
真言宗の開祖、空海(西暦774-835年)は瑠璃を守護石としています。
奈良、正倉院の宝物庫には、紺玉帯と呼ばれるラピスラズリで飾られた黒漆塗の牛革製ベルトが収められています。
日本を目指したマルコ・ポーロ(西暦1254-1324年)はその著書「東方見聞録(原題/百万の書)」の中でラピスラズリについて、次のように書いています。
世界中でもっとも高品質なラピスラズリがこの地方の山で採れる。
(中略)
そこへ行くには岩山の側面を切り出した細い小道を抜け、つり橋を渡らなければならなかった。
(中略)
銀の鉱脈のように縞状になってそれは現れた。
ラピスラズリは、中国では青金石、紺玉と呼ばれシルクロードを通って運ばれ絹などと取引されたわけです。
ところで、このシルクロードという言葉は1877年にドイツの地理学者リヒトホーフェンが東洋と西洋を結ぶ隊商ルートをこう命名したのです。
中国産の絹を中央アジアのオアシスを通じて、イラン、インド、大消費地国であった当時のローマへ運ぶ交易路の一大ネットワークであったわけです。
紀元前2世紀頃、前漢の武帝の匈奴討伐による西域の安定化がその後の活発な東西の交流をもたらしました。
しかし、これまでの話からも分かるように、絹がシルクロードを通じて東西世界を行きかうよりもはるか昔から交易路は存在していたんですね。
交易品としてのラピスラズリが、それまであった中国−インダス、インダス−メソポタミアの交易路をすでに結び付けていました。
絹の需要が交易品としてラピスラズリをはるかに上回るようになり、そのために“シルク・ロード”という名前が有名になっただけです。
そういうわけで、シルク・ロードより以前に“ラピスラズリ・ロード”があった事をここで述べようと思います。
ラピスラズリ・ロード

ラピスラズリの原産地は限られていて、古来アフガニスタンの東北部に位置するバダフシャン地方が主要な産地でした。
なかでもアム・ダリアというアラル海に注ぐ大きな河があり、その支流のコクチャ川上流にあるサル・イ・サング(Sar-e-Sang)鉱山が有名です。
産出された原石は、北はコクチャ川からアム・ダリアを通ってソグディアナのサマルカンドやブハラ方面へ、また、南はヒンドゥークシ山脈を越え、カブールを経てインドやペルシャ、メソポタミア方面に運ばれていたのです。

ペルシアのペルセポリスの遺跡
ラピスラズリがなぜメソポタミア方面にもたらされたのかについては、紀元前500年前後にアケメネス朝ペルシアのダレイオス(ダーラヤワウ)1世が,現在のイラク国境近くにあるスーサに宮殿を造るためラピスラズリを運んだことが碑文に刻まれています。
そのラピスラズリはすべてバダフシャン地方からのものです。
また、紀元1世紀に書かれた『エリュトゥラー海案内記』という文献に、インドの貿易港でラピスラズリが輸出されていたことが記されています。
このラピスラズリも当然バダフシャン地方のものです。
こうしたことを裏付けるように、バダフシャン産出のものがエジプトやメソポタミアばかりでなく、アフガニスタンやイランをはじめとする中央アジアの遺跡から発見されています。
そのうち特に注目を浴びたのが1966年からイタリア調査隊のM・トスィが発掘調査を開始したシャフリ・ソフタの遺跡です。
シャフリ・ソフタはガズニやカンダハルを通る南ルートにあたるのですが、ここからラピスラズリの原石の塊と装飾品に加工するための道具が大量に発見されました。
そのことにより、ここがラピスラズリの一大加工場だったことが分かりました。
また、カーネリアン(紅玉髄)やトルコ石などの原石も多数出土しているので、ラピスラズリだけでなく、その他の貴石の加工もなされていたことも分かりました。
シャフリ・ソフタはイラン国内ですが、アフガニスタンとの国境近くにあります。
アフガニスタンの南部には東北から西南に向かってヘルマンド川が流れており、その下流域はスィースタン(バルーチスタン)地方と呼ばれています。
この地方は現在アフガニスタンとイランとに二分されていますが、シャフリ・ソフタは、そのイラン側のシースタン地方にある城壁に囲まれた都市遺跡です。
遺跡からは50数基の窯跡なども発見されたことから貴石だけでなく、土器の一大加工場であったことも分かりました。
では、バダフシャンよりも
東方については
ラピスラズリがどのように
伝わったのか?

今度はそれを見てみようと思います。
ラピスラズリは中国の書物にも現れます。
1969年に現在の江蘇省の蘇州からいろいろな宝石がちりばめられた硯箱が発見されました。
それにラピスラズリが使われていたのです。
硯箱は重さ約3.5kgの豪奢なもので、現在南京博物館に保管されています。
ラピスラズリが使用された中国の傑作品の一つで、後漢時代(110年代)の明帝の墓から発見されたものです。

莫高窟の大雄宝殿

敦煌市街に立つ飛天像

それから莫高窟の321窟の宝雨経変図に使われている青い顔料を分析してみた結果、ラピスラズリであることが分かりました。
莫高窟のある敦煌が当時国際貿易都市として繁栄していたのです。
そのために顔料が手に入れ易かったのでしょう。
ラピスラズリが大量に使われたのは隋唐時代ですが、のちの西夏時代になると、これに代わって岩碌青という違った岩石が使われるようになりました。
中国のラピスラズリは、バダフシャン地方のものがパミール高原を越えて東トルキスタン即ち西域地方に伝わり、そこからさらに中原地方へもたらされたものと考えられます。
そうすると、バダフシャンと中国とを結ぶルートも、ラピスラズリの道として重要な交易路と言えます。
さらに東に眼を向けると
どうなるでしょうか?

つまり、中国を経由する日本への交易ルートです。

ところで、世界で最も古くガラスが作られたのは,紀元前2300年代以前にさかのぼると言われています。
また、カットによってガラス容器の表面を飾る技法は、紀元前8世紀ごろ始められたと言われています。
バビロニアのサルゴン王(紀元前722−705)の時代に透明なガラスが出来、カットの技法により削り出し、容器に仕上げる方法が発達しました。
この技法はペルシャのアケネメス王朝(紀元前558−331)のガラス工芸にも受けつがれ、素晴らしいガラス器を生み出すことになります。
ペルシャのササーン王朝時代(226−651)には、アケネメス時代のカットグラスが更に発展し、盛んに製作されるようになりました。
私たちが訪れる奈良の正倉院に現存する、上に示した紺瑠璃杯(こんるりはい)は、このササーングラスの一つです。
(現物はもう少し色が濃いです)

正倉院というのは、ご存知のように聖武天皇の宝物などを収めた校倉(あぜくら)造りの建物です。
同天皇が没した756年にはすでに建立されていたということが、最近の研究によって分かりました。
この上に示した紺瑠璃杯(こんるりはい)は4世紀か5世紀に作られたらしいのです。
従って、もし、4世紀に作られていたとすれば、それが、何百人かの商人の手を経て300年から400年かかって、上のシルクロードをたどりながらペルシャから大和へもたらされたことになります。
このガラスに顔料として使われているラピスラズリ(瑠璃)は当然それ以前にも交易品としてもたらされていたでしょう。
こうして見てくると、中央アジアのバダフシャン地方を中心にアジアから西方へ行くルートと東方へ延びる道が1本に結びつくラピスラズリ・ロードがあった事が良く分かります。
シルクロードとして知られる交易ルートがそれ以前にもラピスラズリを交易するためのルートとしてすでにあったと言うことはあまり知られていないようですね。
そう言う意味で、ラピスラズリを考えてみることは大切だと思います。
古代へのロマンをさらに膨らませてくれるのではないでしょうか?
初出: 『ラピスラズリとラピスラズリ・ロード』
(2005年6月17日)
(すぐ下のページへ続く)